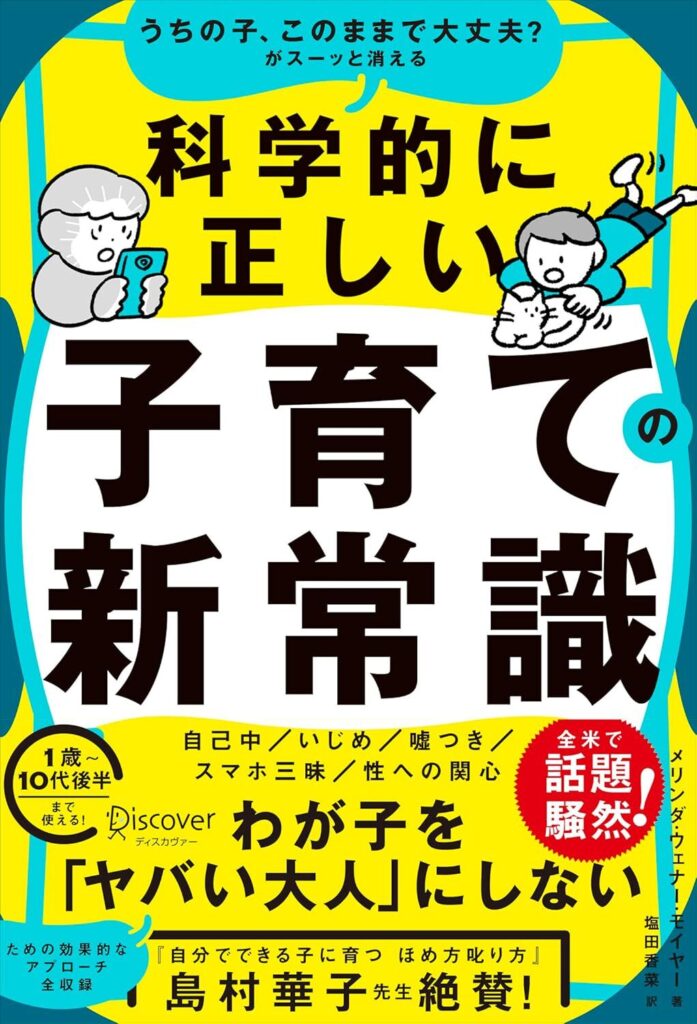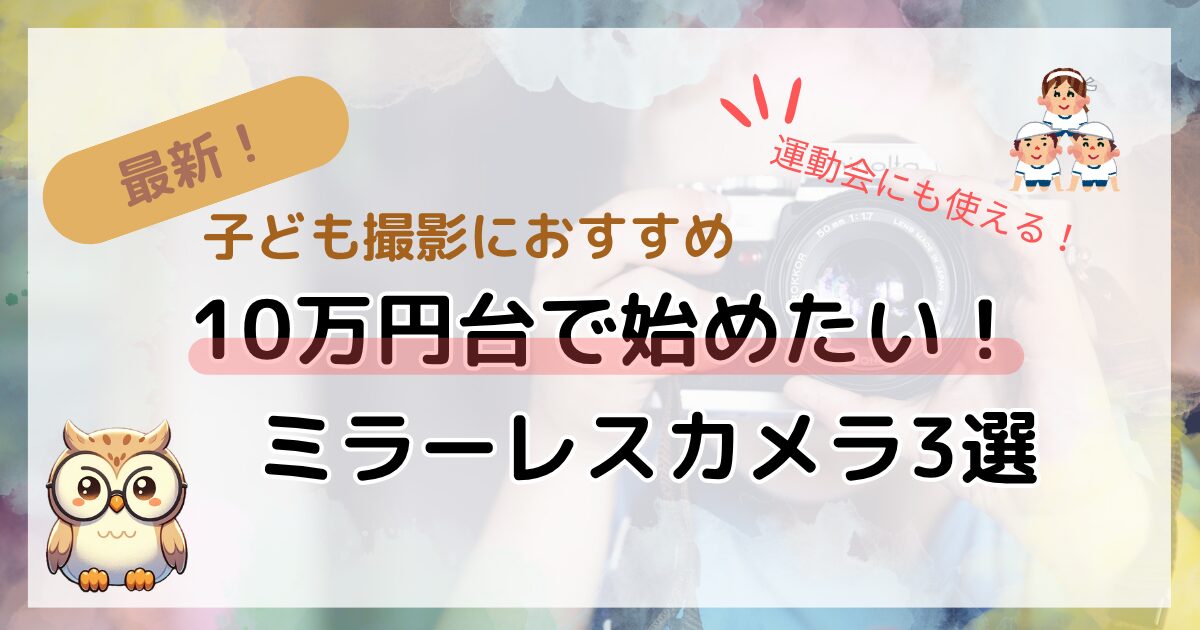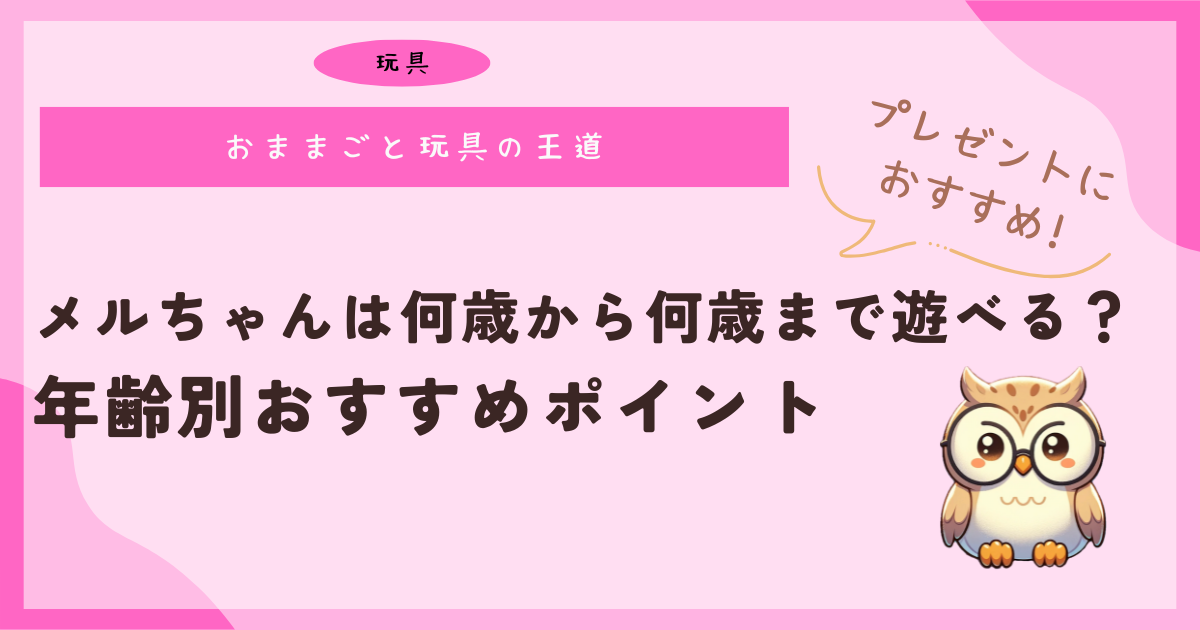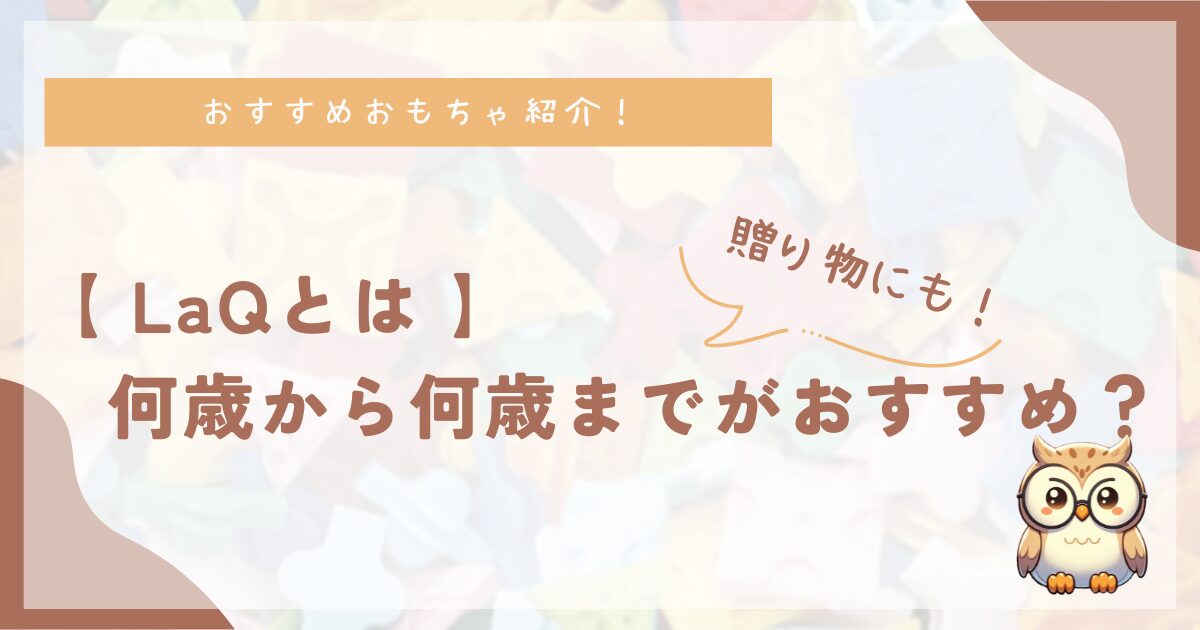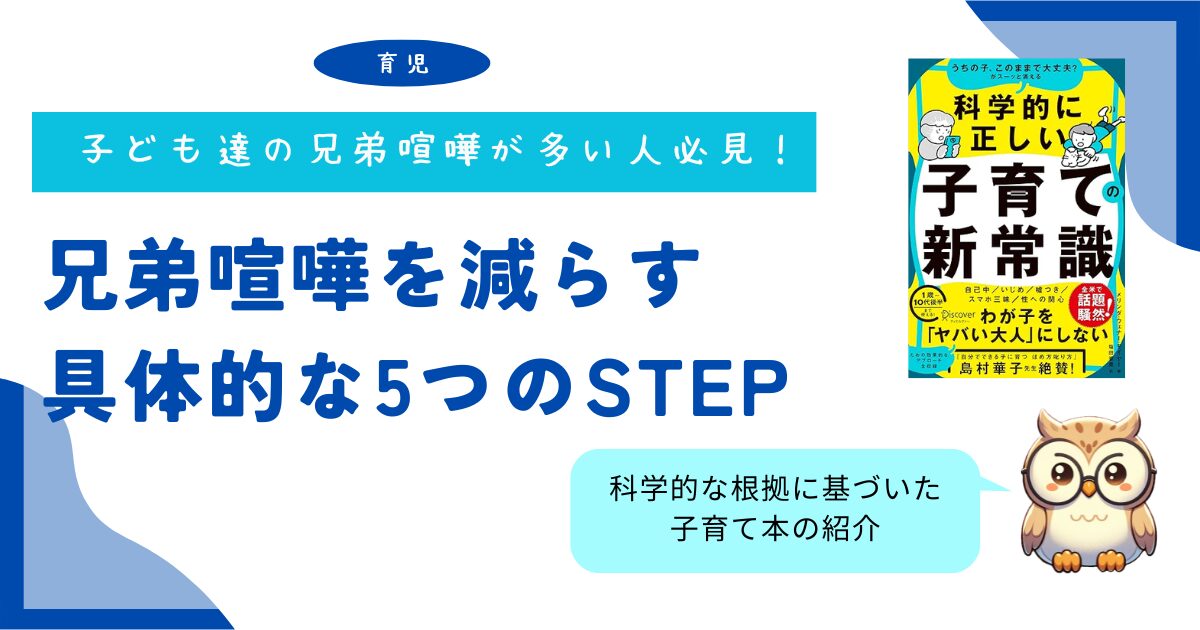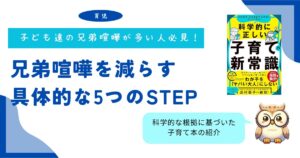お子さんが成長してきて兄弟喧嘩が増えてませんか?
兄弟喧嘩すると自分もなんだかイライラしますよね。
私にも3人子供がいますが本当にイライラして「自分はダメな親なのかな〜」
と自己嫌悪することも1度や2度ではありません。
今回は兄弟喧嘩の減らし方について科学的根拠に基づいて解説したいと思います。
教育はそれぞれのご家庭で方針が異なると思いますが、
具体的な方法を記載しますのでどれか一つだけでも試してみてはいかがでしょうか?
それでは始めていきましょう!よろしくお願いします。
1.兄弟喧嘩はごく普通なこと
そもそも兄弟喧嘩について完全に防ぎ切ることは難しいです。
研究によると、兄弟喧嘩はごく自然な現象であり、感情制御が未熟な子どもが同じ空間で過ごす以上、衝突はあります。
家庭は複雑な人間関係の場であり、子ども同士の欲求の違いもケンカの原因になります。
実際に、1歳半から4歳のきょうだいを観察した研究では、1時間に6回以上のケンカが確認されました。
家庭に常に穏やかな空気が流れるわけではなく、緊張感のある場面もあります。
以上から兄弟喧嘩はごく自然なことで、親がそのことについて自己嫌悪する必要は全くありません。

2.親は審判するのではなく、仲裁を。
一番大事なのは、親が「どちらが悪いか」を決めるのではなく、
子どもたちが自分たちで落ち着いて話し合って解決できるように手助けすることです。
つまり親の役目は仲裁することになります。
仲裁には以下のステップがあります:
STEP1.「相手の気持ち」を考えさせる
兄弟ゲンカを減らすには、「相手の気持ちを考える力」を育てることが大切です。
親は「相手にはどう見えるか」を子どもに問いかけ、気持ちを言葉にさせることが効果的です。
たとえ上の子が赤ちゃんに対して怒ったりしても、その気持ちを受け止めつつ、「赤ちゃんが痛い思いをするから叩いてはいけない」とやさしく理由を伝えるのがポイントです。
上の子の感情も大切にし、両方の子どもの気持ちを理解してあげることが、きょうだい仲を深めるカギです。
以上からまずは「相手の気持ち」を考えさせましょう。
STEP2.兄弟を比べない
兄弟を比べることは、子どもの自信・やる気を失わせる原因になります。
親が「妹は〇〇が得意だね」と言うと、兄は「自分には得意なことがない」と感じてしまうこともあります(親自身そう思っていなくてもです)。
特に「なんでお兄ちゃんみたいにしないの?」などの言葉は注意が必要です。
比べることで子どもは劣等感やライバル意識を持ち、自分の良さを見失うことがあります。
親は、それぞれの子の個性を認め、比べずにその子らしさを大切にしてあげることが大切です。
以上から子供を兄弟や他の子と比べないようにしましょう。
STEP3.公平に向き合うこと
子どもは公平に扱いましょう。
子供は親の行動にとても敏感で、「兄弟で不公平に扱われている」と感じると、自信が下がったり不満を持ったりします。
注意点としては「平等」ではない点です。同じように接するのが「平等」、その子に合った対応をするのが「公平」です。
例えば、赤ちゃんには特別な世話が必要でも、上の子には理由を伝えたり、他の形でフォローしたりすることが大切。
子どもが「自分も大切にされている」と思える工夫が親には求められます。
一人一人にあった対応を行いましょう
STEP4.本人に決めさせること
おもちゃの取り合いで子どもがもめたときなどは、子どもたちが自分たちで話し合って決める機会をつくることが大切です。
親がすぐに判断すると「不公平」と感じさせてしまうことがあり、子どもの成長のチャンスを奪うことにもなります。たとえケンカになっても、子ども同士で「どちらが先に使っていたか」「次は誰が使うか」を話し合いで解決することで、自分の気持ちや他人の立場を理解する力が育ちます。
特に「譲るタイミングを子ども自身に決めさせる」ことがポイントです。
STEP5.仲裁者になること
兄弟ゲンカに親が関わるときは、「どちらが正しいか」を決めるのではなく、
子どもたちが自分で話し合って解決するようサポートする「仲裁役」になることが大切です。
親が一方の味方をしたり、すぐに判断を下すと、子どもは「自分ばかり責められる」と感じ、不満を抱きやすくなります。
実際に研究では、仲裁が効果的で長く良い影響をもたらすことが示されています。
親は冷静に見守り、子どもが感情を落ち着けて相手の気持ちに耳を傾けられるよう促しましょう。このプロセスを繰り返すことで、子どもはケンカの中で人間関係の大切なスキルを学ぶことができます。
このように、親はケンカの「裁判官」ではなく、「手助けする人」になることが大切だということです。
最後に 〜参考文献の紹介〜
本日紹介する内容は以下の文献を参考にしています。
子育てに関するノウハウを科学的根拠をベースに出しており、説得力のある良書です。
ぜひ、読んでいただくといいと思います。